ジェレミー・スタイグが死んだ。
公式サイトによると4月13日だったようだ。詳しい死因は語られていないが、夫人との平穏な日々を綴った残されたブログを読むと、どうやらなにかの病気のために死期をあらかじめ悟っていたらしい。
私が 初めて聴いたジェレミー・スタイグのアルバムは、彼のデビュー作『フルート・フィーバー』だった。「モズ/MOZZ」のオババがよくこれをかけた。
客の誰かが「ママ、立松和平さんが『モズ』のことを書いているよ」と言って、『カイエ』(冬樹社)の1979年1月号を差し出した。「特集・ジャズの死と再生」と表紙に書かれたその冊子をめくってみると、立松和平はこんなことを書いていた。
早稲田の学生の頃は、大学の近辺にある「モズ」という小さなジャズ喫茶にいりびたっていた。ボックスが三つほどと、カウンターに席が五つほどだが、満員のことはまずなかった。壁も天井も煤けたような黒塗りだった。本を読むには暗すぎ、一杯のコーヒーでぼんやりとねばっていた。当時ぼくはいれあげていた少女といつもいっしょにいた。話すこともなく気詰まりになるのを恐れて、ジャズの中にいたのかもしれない。
「モズ」でぼくは一人の奏者と出会った。ジェレミー・スティグというフルート吹きだ。彼のことはレコードのジャケットの解説文以上の知識はない。彼は自動車事故にあい、顔面がほとんど麻痺してしまった。フルートは無理だ。ジャズへの想いはたちがたく、彼はとうとう喉から直接息をとるマウスピースをつくった。
溜がないため、ひどく性急な演奏だ。苦しそうなあえぎのようなスキャットが混じった。吸う息までが音になり迫力があった。それが闇雲な情熱を感じさせた。
ぼく自身、あふれでる生命力をもてあましていた。時代がそうであり、街頭にでれば行き場のない熱気が渦巻いていた。まるで爆薬を小さな箱に詰めているかのように、ぼくは暗いボックス席に少女とすわりつづけていた。店の女の主人はぼくの顔を見るなりジェレミー・スティグをかけてくれた。三四枚別のリクエストをとってから、またかけてくれた。ジェレミーのアルバム「フルート・フィーバー」だ。フルートの熱。三十センチの黒い円盤に爆薬のようにぎっしり詰まった熱気だった。
これを私が読んだのは立松和平が『遠雷』で1980年の野間文芸新人賞を受賞し、その名前が売れ始めたころだったと思う。テレビ朝日「ニュースステーション」が1986年から始めたシリーズ、「こころと感動の旅」のキャスターに立松が抜擢されて全国的な人気を集めるよりも少し前のことだった。
モズのオババに立松和平を知っていたかと聞くと、「覚えているわよ。ワッペイさんね」と言った。
「店の女の主人はぼくの顔を見るなりジェレミー・スティグをかけてくれた。」と立松が書いてあるように、モズのオババは誰が何をリクエストしたかはいつもよく覚えていた。

ジェレミー・スタイグの『フルート・フィーバー』が発表されたのは1963年だ。よくリクエストがかかったアルバムだったのでハッキリ覚えているが、「モズ」にあったのは国内盤のオリジナルで、ペラペラと薄い紙のジャケットの裏面に「フルート・フィーバー」という大きな日本語タイトルとその下に日本語ライナーノーツが印刷されていた。
立松はきっと「モズ」のボックス席に座り、そのジャケットを眺めながらスタイグのプロフィールを知ったにちがいない。
だが、「モズ」についての立松の記述には不正確なところがある。「ボックスが三つほどと、カウンターに席が五つほど」とあるが、カウンターはたしかに5〜6人座れたが、ボックスは4人掛けが4つ、2人掛けが2つあった。
「モズ」の間取りを説明すると、入り口からすぐ左脇にカウンターがあった。その後ろに並行するかたちでほぼ長方形のスペースがあり、向かって奥の右端の天井下にスピーカーが取り付けられていて、その下に4人掛けボックス席が2つ横に並べてあった。そのボックスとボックスの隙間に椅子を一つ入れて、壁側は5人掛けのベンチシートになっていた。そして中央に4人掛けボックスが2つ、左端に2人掛け席が2つ置かれていた。
入り口からすぐの右脇に小さなテーブルを挟んで席が2つあったのだが、そこはたいてい、カウンターでひと仕事を終えてヒマになったモズのオババか、常連の中でもごく限られた人間が座っていた。
少女とぼくとは「モズ」から学園のサークル室やバリケードにでかけていった。血管の中にはいつも「フルート・フィーバー」が駆けめぐっている気がしていた。
コンパで酒を飲んだ帰り、ぼくは少女を強引にホテルに誘って逃げられた。夜道を駆けながらタクシーにむかって手をあげた少女の後姿を覚えている。よくある馬鹿な話にはちがいないが、自分のことだけに思い出すたびキャッと叫びたくなる。それで終りだった。泡のようなものだった。
それからぼくは「モズ」に一人でいることになった。ジェレミーの新入荷のアルバムが入った。「ホワァッツ・ニュー」だ。新しいとは何だ、新しいなんてありゃしねえさ、とそのタイトルからジェレミーの意気ごみが伝わってくる気がした。バド・パウェルとの共演だ。聞いてみてがっかりした。フルートとスキャットが混然となった滅茶苦茶な熱気が影をひそめていた。こちら側に原因があるのかと思い、くりかえし聞いたが、やはり駄目だった。
ジャズに詳しい人ならすぐにわかると思うが、「バド・パウェルとの共演」はまちがいで、共演相手はビル・エヴァンスだ。また、「What’s New」というアルバム名を「新しいとは何だ」と直訳しているのもひどい。これは「元気?」「最近どう?」という、親しい相手への挨拶に使う慣用句だ。もちろん第一の責任は執筆者本人にあるが、もしかして編集者が原稿を読んではいなかったのではという気もしてくる。
ここまで引用してきたのは、「DANCING古事記」と題された一文からである。「DANCING古事記」とは、1971年に発売された山下洋輔トリオ名義の第1作となる自主制作盤だ。
バリケードの中のジャズ
1969年7月、第2次早大闘争と呼ばれる学生運動の渦中にあった早稲田大学において、中核派から分離した反戦連合が、早稲田大学大隈講堂にあった、今では「早稲田の至宝」と呼ばれるドイツ製グランドピアノ、ブリュートナーを盗み出して民青(日本民主青年同盟)がバリケード封鎖している法経4号館に運びこみ、約1時間20分にわたって山下洋輔トリオのコンサートを行なった。
そのときの実況録音盤が「DANCING古事記」である。
この出来事は当時テレビ番組のディレクターだった田原総一朗によって撮影、編集され、東京12チャンネルの『ドキュメンタリー青春』シリーズの中で「バリケードの中のジャズ〜ゲバ学生対猛烈ピアニスト」として同年7月18日に放送された。
もともとは〝ハプニング〟を狙った田原総一朗が仕掛けたものだった。
肺浸潤という肺の疾患による1年半に及ぶ闘病生活を終えてカムバックしたものの、スランプに陥り、突破口を求めてもがいていた山下洋輔を起用してドキュメンタリーを制作したいと考えた田原が、山下がふともらした「ピアノを弾きながら死ねたらいいなぁ」という言葉を受けて、面識のあった反戦連合のリーダー、彦由常宏に「山下さんが弾きながら死ねる状況が作れないか」と相談したところ、この企てが出てきたという。
民青の本拠の地下ホールで反戦連合にピアノ演奏会を開かれたら、民青の面目は丸つぶれである。当然ながら民青は演奏会を阻止するためにはゲバルトをかけてくるだろう。エネルギッシュにピアノを弾いている山下をはさんで、反戦連合と民青の学生たちが石やゲバ棒で肉弾戦を繰り広げる。そんな中で、山下は願望通り死ねるかもしれない。いってみれば乱暴きわまる企てである。もちろん機動隊が導入されて、私が捕まる危険性もあった。
田原総一朗『メディアと権力』講談社より抜粋
いまはYou Tubeで「バリケードの中のジャズ」で検索すると、この放送作品のハイライトである、約7分の演奏シーンを見ることができる。
演奏が終わった後の、心なしか拍子抜けしたかのように聞こえる「ゲバルトはなかった。」というナレーションのとおり、田原が期待したような石が飛び交い、ゲバ棒が振り回される肉弾戦はなかった。
ノンセクト・ラディカルの目印である黒いヘルメットをかぶった反戦連合の学生たちが、山下トリオを囲み、頭を垂れるようにしてその演奏を静かに聴き入っている様子が映し出されているだけだ。
山下トリオのテンションの高さが伝わる緊迫感のみなぎった映像だが、音声では中村誠一がソプラノサックスを吹きまくっているのに、映像に出てくる中村はテナーサックスを吹いているという、音楽的にはかなりずさんな編集となっている。
聴衆の服装はヘルメットにゲバ棒だが、演奏の場面で三十分間をうめても少しも面白くない、と判断した田原氏は、仕方なく、この場面をクライマックスにしたお涙頂戴劇を作ることにしたらしい。女房に内職させたり、八百長電話をかけて来て断わらせたり、医者にこれ以上演奏すると死ぬぞ、といわせたりぼくを多摩川土手に連れってって夕日に向かって走らせたり、寝ころがってセンベイを食わせたり、無理やり連れてきた学生達と飲み屋で議論させたり、ぼくは言われるままにした。そんな事いやだ、とわめいて田原氏に飛びかかったとしてもそれは面白い場面としてテレビに映るだけなのだ。そういうやり方をする人である事は調査ずみである。
しかし、このマスコミの権化のような人とのつき合いは決して不愉快ではなかった。むしろ、色々な事を教えてもらい、感謝したい位である。
山下洋輔/真相「今も時だ」早稲田文学1971年6月号/『風雲ジャズ帖』音楽之友社所収より抜粋
田原総一朗もこのドキュメンタリーに「ヤラセ」が多くあったことは認めている。だがそれでも、真夏の暗い地下のホールで、溢れ落ちる大量の汗をぬぐう暇もなく眼鏡をかなぐり捨てながらブリュートナーを遠慮なく弾きまくる山下洋輔の映像は後世に残すべき記録といっていいだろう。
田原によると、当時からこのブリュートナーは門外不出とされていて、ピアノを置いてある部屋の鍵をなくした警備員がクビになったことがあるという。
1979年10月、私が所属していたジャズ研サークル「現代ジャズ愛好会」が、AACM 創設メンバーのひとり、ムハール・リチャード・エイブラムスを招いて大隈講堂で彼のピアノによるソロ・コンサートを主催したときも、このブリュートナーだった。「フルコン」と呼ばれる仕様の、大きなホールで使われる「フル・コンサート・ピアノ」で、ライブハウスによく置いてあるグランドピアノよりも大きくて長い。私にとってそれは初めてみる「フルコン」で、どこか異様な貫禄があった。
当時は「よそにはない珍しいピアノ」程度のことしか聞いておらず、私はずっと長い間「ベーゼンドルファー」の年代ものと勘違いをしていた。
フルトヴェングラーから「よく歌うピアノ」と絶賛されたブリュートナーは、「アリコートシステム」という独自の設計を採用している。最高音域で通常ハンマーによって打弦される3本の弦に加えて、打弦されることのない1本の弦(アリコート弦)を追加した構造だ。
このアリコート弦が、打弦された弦に共鳴することによって倍音が増幅され、特有の暖かく豊かな響きがもたらされる。
ブラームスやドビュッシー、プロコフィエフが愛用し、奇しくも「バリケードのジャズ」と同じ1969年にビートルズが映画『レット・イット・ビー』の撮影と録音で使用したこしたことでも知られる世界ピアノ4大メーカーのひとつブリュートナーは、近年ヨーロッパではスタインウェイに次ぐ人気となっており、日本でもようやくその真価が認められているようだが、その貴重な年代ものに肘打ちをくらわすなどの乱暴狼藉を働いたのが、この 1969年の山下洋輔のパフォーマンスということになる。
田原総一朗によると、大隈講堂からこのブリュートナーを運び出した学生たちの中に中上健次が加わっていたという。また山下洋輔によると、高橋三千綱や連合赤軍リンチ殺人事件(山岳ベース事件)の犠牲となった赤軍メンバー、山崎順もいたという。さらに北方謙三や伊集院静もピアノを運んでいたという説もあるが、ここまでくるともう、真実はわからない。
だが、立松和平は、その場には居合わせなかった。
「ぼくはそのコンサートにいっていない。たぶんバイトか何かしていて知らなかったのだ。後で聞いてほぞを噛んだ。」とこの『カイエ』に書いている。
しかし立松は、「DANCING古事記」の制作にかかわった重要人物の一人だった。そのことの顛末を振り返るというのが、この一文の主題だった。

原稿依頼をしたのは、『カイエ』編集長で立松と同い歳だった小野好恵だろう。
小野は、1975年から編集長を務めた『ユリイカ』で「ジャズは燃えつきたか」(1976年1月号)、「ジャズの彼方へ」(1977年1月号)などのジャズ特集で注目された後、1978年に青土社から冬樹社に移り『カイエ』を創刊、1980年第20号の山下洋輔特集号で休刊となるまで同誌でもジャズ特集を積極的に組んだ。
1996年に49歳の若さで病死した小野は、阿部薫のアルバムのライナーノーツへの執筆をはじめ(一関のジャズ喫茶『ベイシー』菅原正二店主によると小野が阿部を『ベイシー』に連れてきたこともあるという)ジャズや文芸、プロレスなどを中心に執筆、編集活動を行ない、ジャズの造詣も深い文芸編集者として、70年代からその死にいたるまで日本のジャズ言論界に大きな足跡を残した。
また、文芸にとどまらず、ジャズやビートルズ、映画、SFなど、ポップカルチャーについて文学者や詩人、作家、哲学者、思想家に原稿を依頼して特集を組むという小野が手がけた70年代の『ユリイカ』や『カイエ』の編集スタイルは、80年代以降に続々と登場したハイ・カルチャー雑誌の先駆けとなる仕事をしたといえるのではないかと思う。
1947年生まれの小野は、同世代の作家、村上春樹(1949年生まれ)と親交があった。
まだ村上が国分寺でジャズ喫茶「ピーター・キャット」を経営していたころからの付き合いで、単行本『ジャズの事典』(1983年、冬樹社)では、「かつてジャズはつねに制度を拒みそれを乗り超えてきたものだったんだ」と題したインタビューで、胸襟を開いた村上春樹からジャズ喫茶経営時代の話や彼のジャズ観などを8ページにわたって聞き出すという、貴重な仕事をしている。
また、小野は村上龍(1952年生まれ)とも親交があつく、「ピーター・キャット」に彼を連れて遊びに行くこともあったという。
1979年の群像新人文学賞のパーティー会場で、小野と村上春樹がいっしょにいるところに出会った村上龍が、「こんなところで何をしているんですか?」と村上春樹に尋ねたら、小野に「バカだな、この人が受賞者だよ」と笑われたという逸話が残っている。(村上龍著『文学的エッセイ集』シングルカットより)。
同書によると小野を村上龍と引き合わせたのはジャズ評論家清水俊彦だった。その場には小野を『ユリイカ』編集部に引き入れた元ユリイカ編集長三浦雅士と、のちに《スーパー・エディター》と称してジャズ言論界に参入してきた中央公論社の文芸誌『海』の編集者安原顯の2人もいた。
DANCING古事記プロジェクト
立松の記述に戻ろう。
演奏から一年半たっていた。小説が機縁になり、あの演奏の録音が見つかった。山下洋輔の手元にあったのだったか。ともかくぼくらには発見だった。テレビ局がとっていたものだった。夜、阿佐ガ谷のアパートに集まって仲間たちと聞いた。いい演奏だった。いろんな事情を抱えて学園を去り一年以上もとりとめもなくさまよっていたぼくらには、衝撃的だった。熱病だった。レコードにしようといいだしたのはぼくだ。金を払ってレコード会社に頼めば、セルロイドを型に流しこむようにいくらでもできるはずだ、と思った。同席していたトリオの連中も喜んでくれた。
立松がここに書いている「小説」とは、彼が『新潮』1971年3月号に発表した「今も時だ」のことだ。
セクトが占拠している校舎に突っ込んでコンサートを開くという設定で、立松によれば「ほとんどアドリブで一気に書き上げた」という。「今も時だ」というタイトルは、おそらくチャーリー・パーカーが残した傑作曲「Now’s The Time」にインスパイアされたものだろう。
1970年の夏に書かれたものだが、前年の法経4号館地下でのコンサートを目撃できなかった立松は、そのうっぷんを晴らすかのように、石がうなり火炎瓶が炸裂し、最後にはピアニストが血を吐いて昏倒するというフィクションを創り上げた。
新潮新人賞候補作になり、立松本人は絶賛を浴びるものと確信していたが、選考委員からは「稚拙」と講評され、あえなく落選した。だが、この「今も時だ」がきっかけとなって「DANCING古事記」プロジェクトが動き始めた。
麿赤児を社長にして麿プロを作った。もちろん法人などではない、でっちあげの集まりだ。ぼくらが麿プロと呼んだから麿プロといったにすぎない。最初事務所はぼくのアパートにあった。当時の僕は新婚だった。駆落ちして死ぬの生きるのと大袈裟に騒ぎ、女の親に許されてかたちばかりの祝言をあげたばかりだった。やっと落着いて所帯を持ったばかりのアパートに、麿赤児や森山威男や中村誠一や山下洋輔やそのほかうすぎたない連中がわんさといりびたる。ちょっとやばいではないか。ぼくは地下鉄南阿佐ガ谷駅近くに必死でアパートを見つけ、電話を移転した。猫の小便のにおいがきつい北向きの六畳だった。隣の印刷屋の庭にいつも猫が群れていた。麿赤児はアジの干物をエサによく猫釣りをした。
麿赤兒が猫釣りをしていたのは、三味線の腹として業者に売りつけようとしていたからだと立松はのちに自伝的小説『蜜月』(集英社)で書いている。このころの麿は、唐十郎の状況劇場を退団したばかりだった。「大駱駝艦」を旗揚げする少し前である。
60年代から「モズ」には演劇関係者が多く来た。モズの天井や壁には、ジャズと同じぐらい演劇関係の公演ポスターがたくさん貼られていた。チラシやポスターを置いてくれと店にお願いをするのがきっかけで彼らはモズのオババと言葉を交わすようになり、やがて客として来るようになった。
私がいた頃は、状況劇場の団員たちがよく来ていた。大駱駝艦の人もいた。物静かだった彼らがカウンターに座ることはまずなく、独りで隅っこの2人掛け席にじっと座っているか、誰かと一緒に来たときもボックス席で穏やかに談笑しているのが常だった。騒々しいジャズ研の学生たちと交わることはほんとどなかった。
事務所を開設したものの、金もなしでレコードをつくるのは並大抵ではない。セルロイドの円盤だけでなく、ジャケットもいればチラシもポスターも必要だった。ダビングは東京12チャンネルでタダでした。知人の手引きでスタジオがあいている時を見はからって勝手にやったのだ。鴬谷にあったジャケットの印刷屋にいき、社長、金を落としました、クビにしてください、と電話を借りてわざとらしく大声でわめいたりした。電話を印刷屋の親父とかわり、麿赤児がどういいくるめたのか三百枚渡された。レコード盤はもっときびしかった。ぼくらがシナチクレコードと呼んでいたテイチクレコードで、一万円二万円と払って十枚二十枚ともらってきた。事務所のアパートで袋にいれ、各自が持って売りに歩ったりした。
時効だからもういいかと立松は思ったのかもしれないが、これを書いたときはまだ「事件」から10年もたってない。大隈講堂から勝手にピアノを運び出したことも含めて、これらの所業は、いまの世ならまず炎上案件である。
ただ、レコード会社と印刷屋への支払いは苦労したようで、前述の『密月』によると、麿赤兒は妻に小言をいわれながら家財道具一式を担保に入れて「DANCING古事記」の売上金が回収できるまでしのいでいたようだ。
タイトルの「DANCING古事記」は麿赤児の命名だ。意味はどうでもいい。定価二千円、特製LP、限定盤、先着五〇〇名にサイン入り。大好評だった。通信販売で申込みのあった金などをすぐテイチクレコードに持っていった。だが、レコードを売ることは、つくることほどおもしろくはない。三ヵ月か四ヵ月働いてベストセラーにし、一年か二年遊んで暮らすはずだった。レコードはみるみるはけていったが、思ったように金がはいってこない。それでも事務所には得体の知れない連中がわんさか集まってきた。
「DANCING古事記」は、素人同然の集団が手がけた自主制作盤であるため、世には出したもののそのまま人知れず消えていった幻の作品と思われがちだ。実際に、当時のスイング・ジャーナルはこれを黙殺しているようだ。
しかし麿赤兒やマネージャー、有志たちはこのアルバムのプロモーションのために、いわばゲリラ戦を各方面に仕掛けて、それなりの成果を上げたようだ。
早大裏門前から生み出たもの
まだ隔月刊だった頃の『jazz』(ジャズ・ピープル社)の1971年第10号(AUTUMN)では、この「DANCING古事記」と山下洋輔トリオ、そして麿赤兒が大きく取り上げられている。
まず驚かされるのは1ページを使った「DANCING古事記」の広告だ。特集のすぐ後ろには麿赤兒による「母系性ジャズの赤い血の消えぬ間に」という約2ページのジャズ評論、そして「CONCERT REVIEW」では杉田誠一編集長による山下洋輔トリオの公演レビュー、さらに新譜紹介コーナーでは編集部員にレビューを書かせている。


こうした大々的展開は、通常なら1ページの純広告に対するサービスと考えられるが、当時の「麿プロ」の状況からして、正規の広告契約がなされていたかどうかはあやしい。杉田編集長の厚意、肩入れによるものなのだろうか。
ちなみに編集部員の新譜レビューによると、「DANCING古事記」は朝日新聞や平凡パンチにも取り上げられたとある(前述の『蜜月』には、立松がモデルとなる主人公がプロモーションのために大手出版社を訪問するくだりが書き込まれている)。
これらの記事の中で特に興味深いのは杉田編集長よる公演評だ。1971年5月27日に大岡山・東京工業大学講堂で行なわれた山下トリオ公演について、杉田は次のようにその様子を伝えている。
前方舞台上にはござが敷きつめられ、「流民群」の様相を呈してヒッピー風学生たちがべったりと腰をおろし、まわしで一升瓶があけられている。開演に先立ち、主催者側から提供された一升瓶が会場のそこかしこで次々にあけられていく。山下トリオは講堂の客席中央に陣取っていつものようにガンガンと演奏しはじめる。通常使用される舞台上には、黒いシートがかぶせられた椅子に、麿がどっかりと腰をすえて、山下らとむかい合っており、そこから山下の地点に至るまでは直線に観客席を貫いて花道が設置されている。『古事記』ならぬ(河原)乞食を思わせるボロ着物をはおった麿は、始めのうちは座り続けるだけで全く動かなかった。麿の視線が時々移動するつど、見物人には麿の方を見つめざるをえない。山下トリオの面々も含めて、見物人はすっかり麿の肉体に釘付けされてしまった。
杉田が何より驚いたのは、「ジャズは阿片になりうるが、背景にもなりうることを麿によって知らされた。」という言葉で最後を結んでいるように、麿赤兒の「特権的肉体」の存在感だった。
麿赤兒もまたもう一方の主役として、山下トリオをときには凌ぐほどのパフォーマンスを観客の目に焼き付けたに違いない。
麿と山下トリオによる「DANCING古事記」ツアーは、名古屋、京都、新潟などを回ったようだ。
その頃山下のマネージャーを務めていた阿部登によると、山下トリオや阿部たちが新幹線で移動していたのに対して麿たち演劇集団はヒッチハイクで移動していたらしいという話も残っている(北中正和責任編集『風都市伝説 1970年代の街とロックの記憶から』音楽出版社)。
風都市主催による1971年6月5日の「DANCING古事記—東風」と題された京都大学西部講堂公演や翌6日の京都・円山音楽堂公演では、村八分やはっぴいえんどの後のトリとして山下洋輔トリオが出演した。
その当時のことを2007年から2020年まで可児市文化創造センター館長兼劇場総監督を務めていた衛紀生が、「モズ」やそのころ早稲田にあったもう1軒のジャズ喫茶「フォービート」の思い出を交えながら、可児市創造文化センターのホームページにエッセイを書いている。抜粋はせずにここにリンクを張っておく。「エリック・ドルフィーのように。」
「フォービート」は、早稲田通り沿いの「モズ」のすぐそばの交差点から安部球場(1987年に閉鎖されて現在は中央図書館、国際会議場に)の横のグランド坂を下る途中にあったというが、私が入学した1979年よりも数年前に閉店していた。
スタックスのオールコンデンサー型スピーカーが置いてあり、青山南や村上春樹も行ったことがあるらしい。このあたりは早稲田大学正門とは反対側であり、いわば「裏早稲田」といっていい界隈だが、平岡正明が『昭和ジャズ喫茶伝説』(平凡社)で興味深いことを書いている。
ミンガスは、ワセダ安部球場裏のジャズ研や、演劇の連中が屯(たむろ)した、「クレバス」というふつうの喫茶店と、その近く、戸塚二丁目五叉路角にあった「もず」という店で聴くと、「ミンガス実験室」のワークショップたる雰囲気が伝わった。
少人数をもって、エリントン楽団を髣髴(ほうふつ)させるミンガスの実験精神が、ジャズ研や、演劇関係の部室のような喫茶店の、ボロだが、やる気満々の空気感にはまっていた。少人数で、エリントン楽団みたいなことをやるというのは、ようするに貧乏ということだ。貧乏の存在感は鋭いということだ。
喫茶店「クレバス」があって、マージャン屋があって、飯屋があって、学徒援護会の窓口があって、もうちょい行くと早稲田西門(裏門)にぶつかるガレ地に、いろんなサークルが雑居している、でかいだけのボロ舎があった。
「ハイソ」と「劇研」と、少林寺拳法同好会なんかが雑居していた。楽団とハイソとジャズ研は、同じグループの演奏部と鑑賞部だった。
「はれんちカンカン」(平岡立案のダダ劇)稽古中だから、一九六三年春だ。
これによると平岡は、1963年ごろ、詩人の宮原安春、演劇の諸富洋治らと結成した政治結社「犯罪者同盟」のメンバーらとともに演劇やジャズ関係者と交わって、ジャズと詩と演劇を組み合わせた舞台表現に取り組んでいたようだ。
山下洋輔トリオが新宿ピットインや新宿・花園神社境内の紅テントで唐十郎の状況劇場とジョイント公演をやって注目を浴びる1967年よりも少し前のことだ。
のちハイソから、タモリや、小山彰太が出たのも、六〇年代はじめの、早大裏門一体の諸族混交の気風が、いくらか関与しているのだろう。
細かいことだが、平岡は早稲田の「ジャズ研」や「ハイソ」を混同しているようで、タモリと小山彰太は早稲田大学モダンジャズ研究会の出身で同会には演奏部と鑑賞部(私がいた『現代ジャズ愛好会』の前身)があった。「ハイソ」(早稲田大学ハイソサエティオーケトラ)とは別の団体である。
いずれにしても早大を中退し状況劇場を退団した麿赤兒が、山下トリオと「DANCING古事記」で交わったのも、やはりこうした「早大裏門前の諸族混交とした気風」と遠からぬ縁があったのかもしれない。
話がすっかり脇道にそれてしまった。
楽しかった。楽しみすぎて商売には失敗した。テイチクレコードから注文した枚数を全部引取ることはできたが、日に日に電話は鳴らなくなってきた。六畳一間の事務所で在庫の山に途方にくれていた。一枚ずつ売り歩ける場はとうに使いつくし、代金の回収をしてまわる気力も失せた。最後はあるレコード販売会社にまとめて格安で売った。商売にはしくじったが、山下洋輔トリオをおとしめるものではない。名盤なのだ。幻の名盤かもしれない。
「DANCING古事記」プロジェクトが終わって7、8年ほど経った70年代末、ラジオ局に出演した際にこのアルバムをかけてもらい、「いま手元にあったら大もうけできたのになあ」と書いて立松のこの一文は終わる。
山下洋輔、はっぴいえんど、シュガー・ベイブ
「DANCING古事記」はたしかに幻の名盤となった。95年に貞練結社からCDで復刻されるまでは稀少な音源として数万円のプレミアがついて珍重された。いまでもオリジナルのヴィニール盤にはかなりの値がつくらしい。

「モズ」にはこのオリジナル盤が1枚あった。誰が持ってきたのかは判らなかったが、おそらく山下洋輔の事務所「TAKE ONE」の関係者ではないかと思う。
「TAKE ONE」は、山下洋輔のマネージャーだった柏原卓と、はっぴいえんどをサポートしていたことで知られる企画集団、風都市の前田祥丈と長門芳郎の3人が1974年に設立した事務所で、山下洋輔トリオを筆頭に、山下達郎、大貫妙子のシュガー・ベイブらのマネジメントをしていた。
「TAKE ONE」を設立した3人の中では、柏原卓がよく「モズ」に来ていたらしい。店にいるヒマな大学生をつかまえては近所の雀荘に行っていたという話もある。私のサークルの先輩の中には、この柏原とのつながりで「TAKE ONE」のアルバイトをしていた学生が何人かいた。いまはブラジル音楽を中心に活躍している音楽・放送プロデューサー/選曲家の中原仁もその一人だった。
そういえば、「モズ」の近くに70年代のはじめに「TAKE-1」というジャズ喫茶ができたことがあった。
早稲田通りを挟んで「モズ」の反対側にあり、文学部校舎のほうに降りていく坂の途中、アバコブライダルホールに入る路地の角の、焼き肉屋と麻雀屋の入ったビルの3階にあったという。
平岡正明の『昭和ジャズ喫茶伝説』(平凡社)によると、こけら落としのときは渡辺貞夫と山下洋輔がジャムセッションをやったとある。私は、もしや事務所「TAKE ONE」となんらかの縁があるのかと思い、「TAKE ONE」関係者に尋ねてみたことがあるが、どうも直接の縁はなかったようだ。1974年に笹塚に事務所「TAKE ONE」ができる前の話だ。学生たちから「タケイチ」とか「タケオネ」と呼ばれていたジャズ喫茶「TAKE−1」は70 年代の半ばに閉店した。
事務所「TAKE ONE」の特色はジャズとロック双方のジャンルのブッキングができることだった。
たとえば「TAKE ONE」がブッキングを担当していた1974年の荻窪ロフトでは、本田竹曠トリオ、山下洋輔トリオ、佐藤允彦などのジャズ系ミュージシャンと、細野晴臣、林立夫、松任谷正隆、伊藤銀次、矢野誠、小原礼、はちみつぱいなど、いわば「はっぴいえんど/キャラメル・ママ/ティン・パン・アレー」人脈のミュージシャンやシュガー・ベイブなどが日替わりで出演した記録が残っている。
しかし、ジャズ系とロック系のミュージシャンをひとまとめに扱うことにはやはり限界があったようだ。
1976年4月、山下洋輔トリオから森山威男が抜けて、新たなドラマーとして早大出身の小山彰太が加入したのと同じ時期に、事務所「TAKE ONE」から分割するかたちでジャズ部門をマネジメントするオフィス、「ジャムライスJam Rice」が発足した。山下洋輔トリオ(山下洋輔、坂田明、小山彰太)、向井滋春、大野えりなどが所属していて、事務所は確か六本木にあった。
ジャムライスは、アクト・コーポレーションと組んで、1977年から1984年まで、毎年夏に野外ジャズフェスイベント「サマーフォーカス・イン」を日比谷野外音楽堂で主催し、山下洋輔トリオをはじめ、森山威男、国仲勝男、向井滋春、古澤良治郎、リー・オスカー、渡辺香津美、坂本龍一、高橋幸宏、キリンバンド、To-chi-ca(マイク・マイニエリ、ウォーレン・バーンハート、マーカス・ミラー、オマー・ハキム)、杉本喜代志、板橋文夫、近藤等則、松岡直也、本多俊之、大野えり、渡辺文男、高橋知己 、生活向上委員会大管弦楽団、井上敬三などが出演した。
この頃のジャムライスの制作スタッフを現代ジャズ愛好会出身の中原仁が務めていた関係で、「モズ」に出入りする学生たちの中にはこの事務所の手伝いをする者も何人かいた。
79年から82年頃まで、私はこの「サマーフォーカス・イン」をはじめ、グローブ・ユニティ・オーケストラ(1980年)やICPオーケストラ(1982年)などのジャムライス主催公演のポスターやチラシを持って都内のジャズ喫茶やライブハウス、喫茶店を回った。思えば私のジャズ喫茶巡りの習性はこの頃に培われたのかもしれない。バイト料は出なかったが、いまとなっては貴重なライブをバックステージでタダで見られたことや打ち上げでタダ飯が食えたことが報酬だった。
80年代から90年代かけて、「モズ」にやってきてジェレミー・スタイグの「フルート・フィーバー」をリクエストする客がけっこう多かったのは、立松和平が残した『カイエ』の一文の影響もあったのではないかと思う。
また、『DANCING古事記』のオリジナル盤を目当てにやってくる若者も多かった。
彼らはたいてい、リクエストをしながら60年代末から70年代はじめの学園紛争当時のことを熱心に質問する〝遅れてきた青年〟だった。そんなときモズのオババは、にわか観光ガイドみたく変身して、ていねいに自分が経験したことを語ってやっていた。
だがそんなやりとりを横で聞いていた私も含めて、その頃「モズ」にいた学生の大半は、政治には興味の薄いノンポリであり、音盤による快楽の追求を至上とするものばかりだった。
「モズ」も「フォービート」もなくなってしまったが、いま裏早稲田界隈には「JAZZ NUTTY」というジャズ喫茶がある。グランド坂を下りきったところ、蕎麦屋の老舗「金城庵」の向いに2008年にオープンした。
青木一郎店主は早大出身ではなく、獨協大学のジャズ研OBだ。
蒲田で「サッチモ・フラワー」という名の花屋を26年間 経営していたが、敷地拡張工事によって立ち退きを余儀なくされ、それまでなんの縁もゆかりもなかった早稲田でジャズ喫茶を開いた。デューク・エリントンやセロニアス・モンクをはじめとするジャズの王道をマッキントッシュのアンプとJBL4331Bで気持ちよく鳴らす店として、いまや都内のジャズ喫茶の中でもファンの多い店だ。
実は青木店主は大のフリージャズ・ファンで、ふだんは店では扱わないが、その場の雰囲気をみはからってこっそりその手のものをかけるときもあるらしい。
ジャズ研時代にトランペットを吹いていた青木店主は、数年前に早稲田祭のモダンジャズ愛好会のライブに飛び入り参加してぶち切れたフリーキーなプレイを披露、現役学生たちよりも会場を湧かせて評判になってしまったという。
裏早稲田界隈にはなぜか、こういう人が集まってくるようだ。
(次回へ続く)
※文中は敬称略とさせていただきました
text by 楠瀬克昌
関連記事:連載第1回 さらばジャズ喫茶「モズ」のオババ①タモリと久米宏のやりとりの「謎」
関連記事:連載第3回 さらばジャズ喫茶「モズ」のオババ③/軒口隆策、タモリ、モダンジャズ研究会の時代
【写真:西早稲田のジャズ喫茶「モズ」のマッチ/画像提供:松浦成宏】

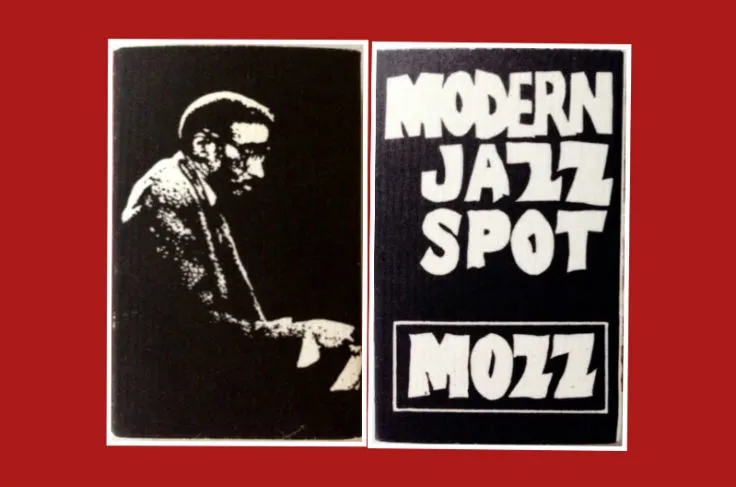









コメント